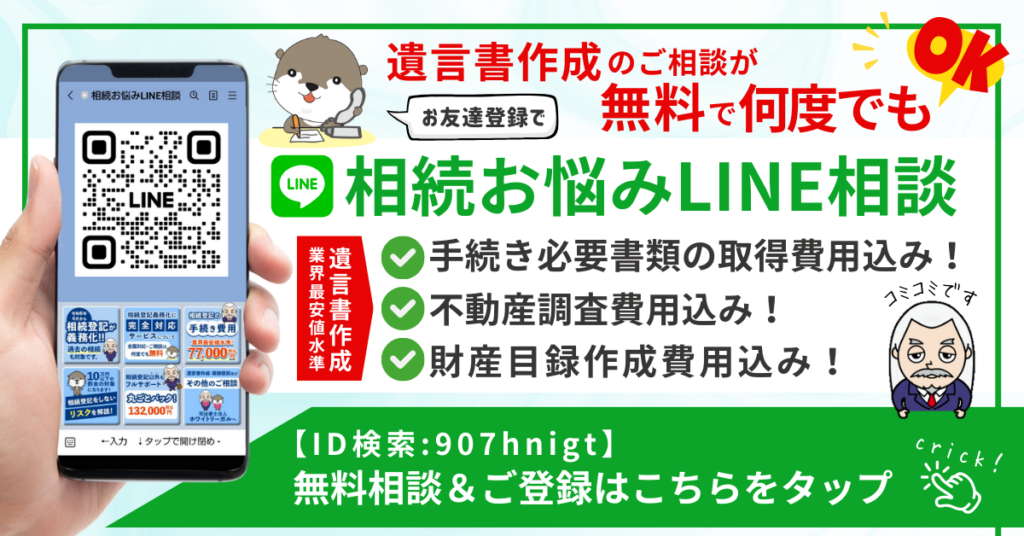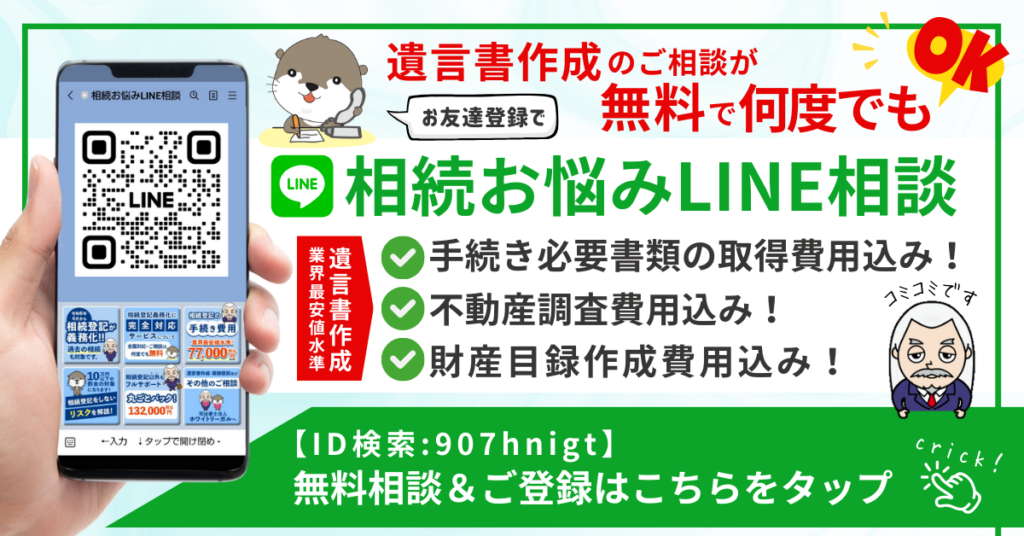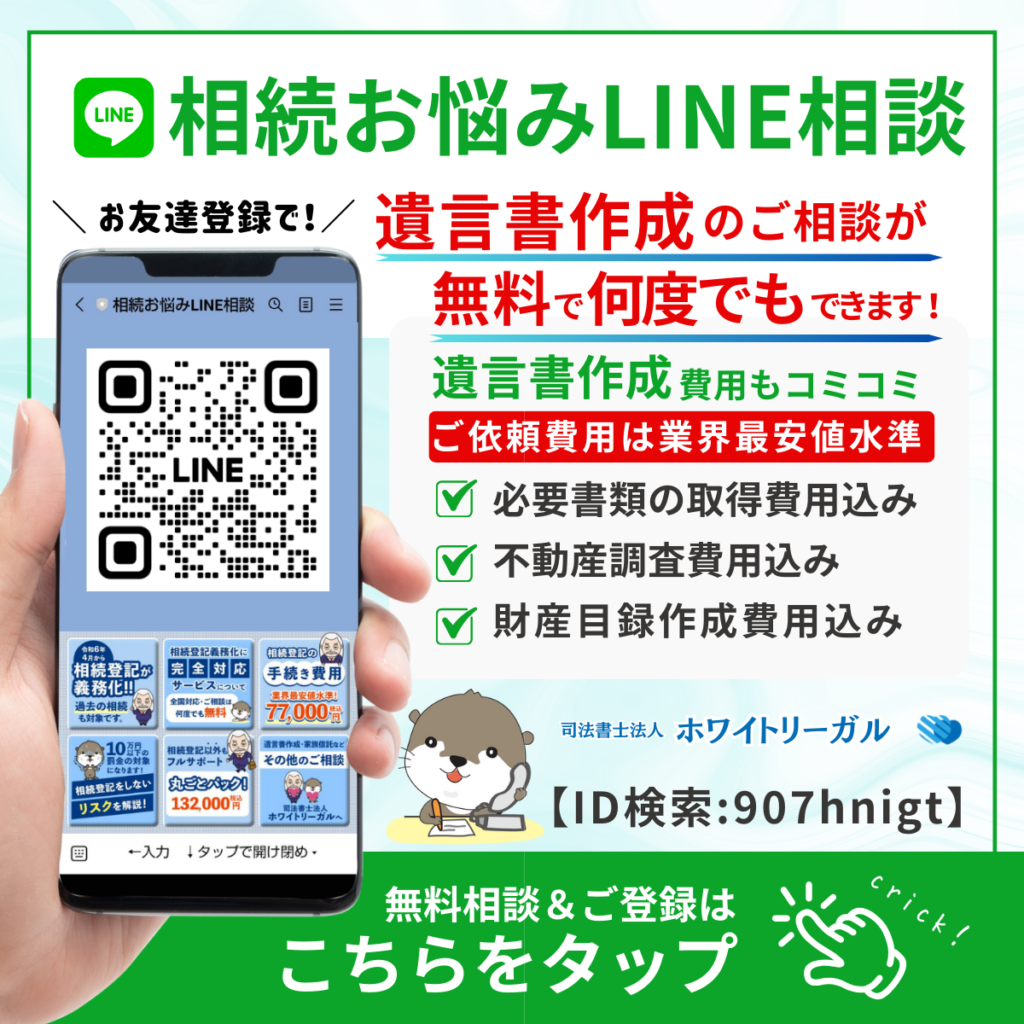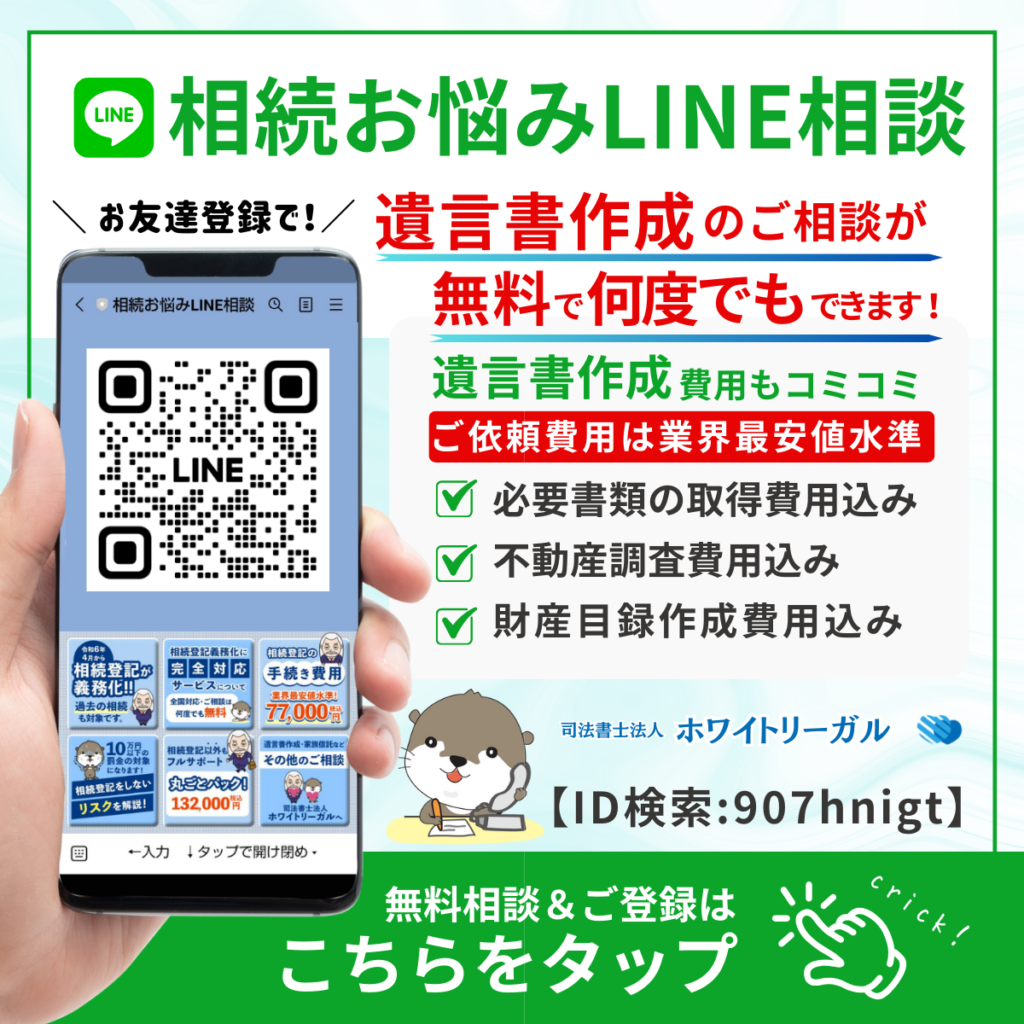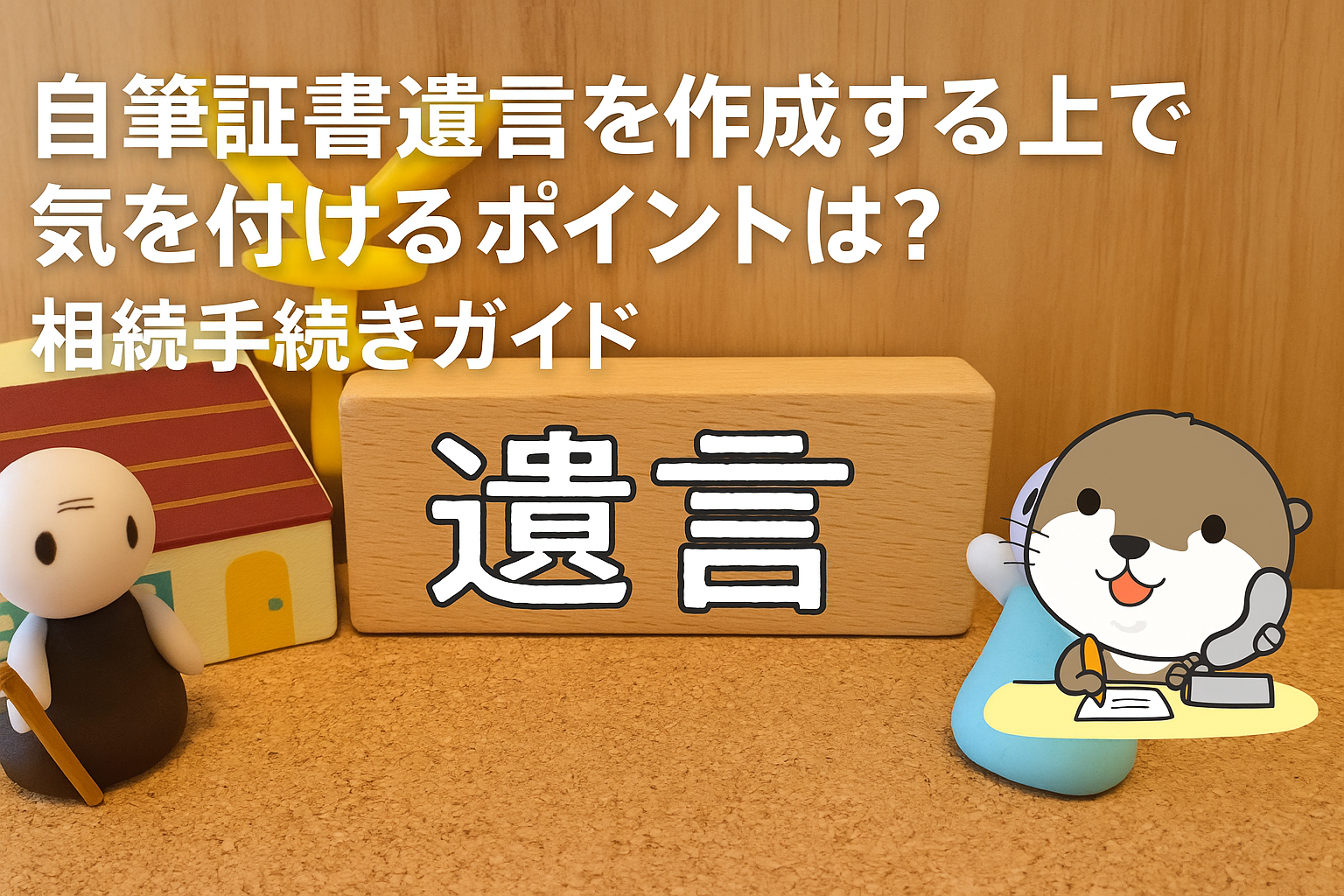こんにちは、「相続手続きガイド」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
「そろそろ遺言書を作っておきたい…」と思っていても、
実際に自分で書くとなると「何を書けばいいの?」「書き方は正しいの?」と不安になりますよね。
今回の記事では、最も身近な遺言の形式である自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)について、
専門家の視点から作成時に気をつけるポイントを、司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
お友達登録するだけで遺言書作成のお悩みが解決できる!相続お悩みLINE相談!
正しい遺言書を残すためのポイントを、司法書士が詳しく解説します!
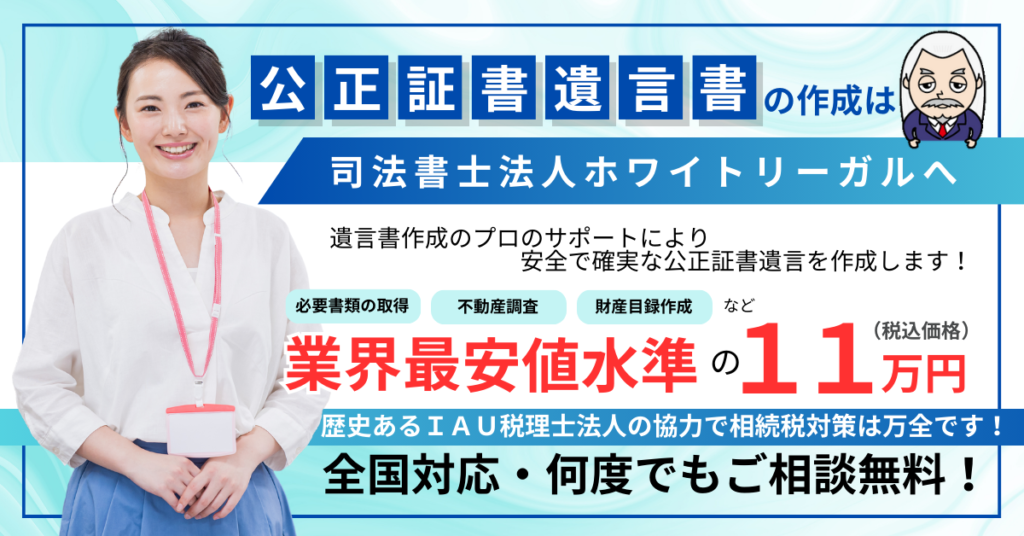
「遺言書作成ご相談のページを少し見てみる!」
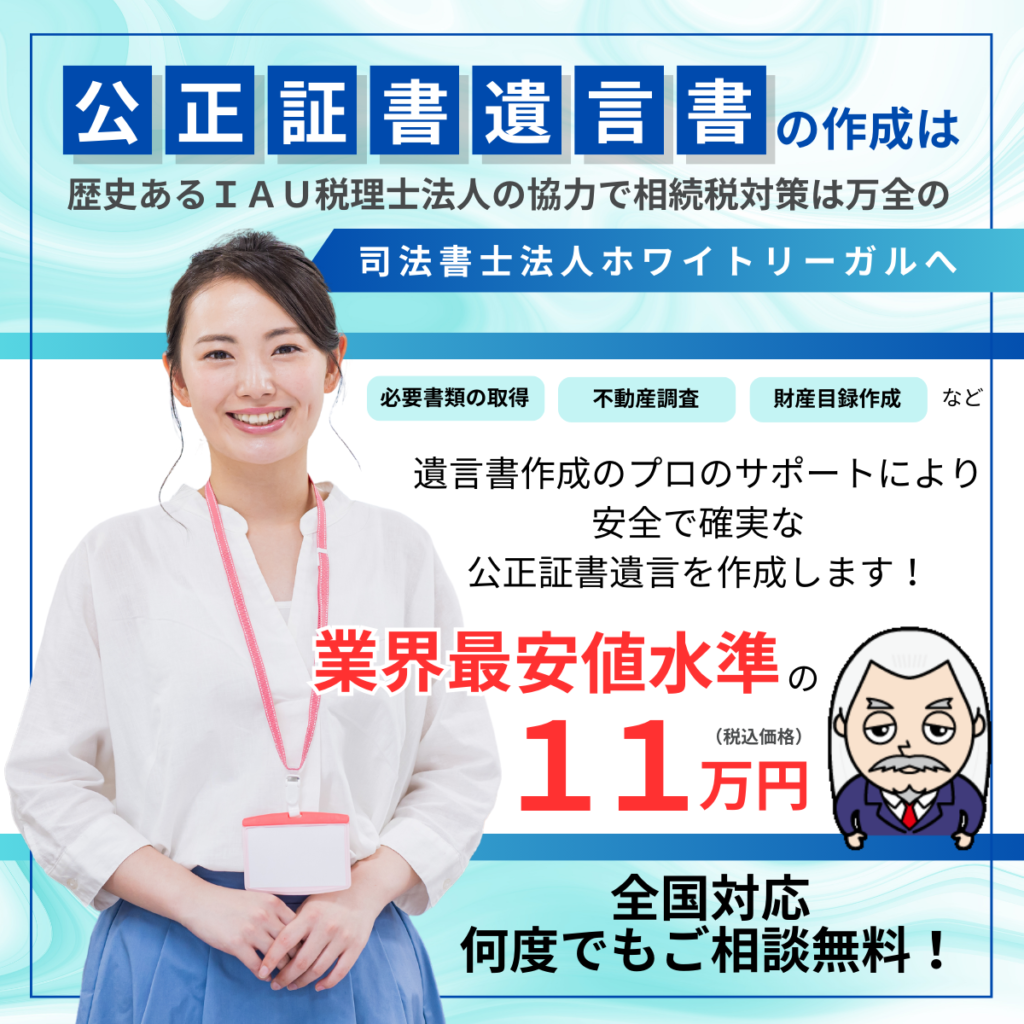
「遺言書作成ご相談のページを少し見てみる!」
自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言とは、遺言者がすべて自分で書いて作成する遺言書のことです。
費用をかけずに自宅で作れるため、一番気軽に始められる方式ですが、ちょっとしたミスで「無効」になるリスクがある点には注意が必要です。
自筆証書遺言の基本ルール
次の4つが最低限守るべき要件です。
- 全文を自筆で書く(手書き)
- 日付を入れる(例:令和○年○月○日)
- 氏名を手書きで書く
- 押印(印鑑)を押す(認印でもOK)
✅ 注意:パソコンや代筆では無効になります。
よくある失敗例と注意点
✖ 日付があいまい
×「○月吉日」などの書き方では無効とされる場合があります。
→ 必ず「2025年7月15日」など特定できる日付を記載しましょう。
✖ 財産の書き方があいまい
×「預金は長男に」「不動産は妻に」だけでは不十分。
→ 金融機関名・支店名・口座番号、不動産の登記情報などをできるだけ具体的に記載しましょう。
✖ 受け取る人(相続人)が特定できない
×「子どもに」だけだと、複数いる場合にトラブルに。
→ 「長男○○ 太郎」などフルネームで明記しましょう。
✖ そもそも書いたことが家族に伝わっていない
→ 遺言書が見つからなければ無効も同然です。
→ 信頼できる家族や専門家に保管場所を伝えるか、法務局の保管制度を活用しましょう。
法務局による「自筆証書遺言保管制度」とは?
2020年から始まった制度で、法務局に自筆証書遺言を預けておける制度です。
メリット:
- 家庭裁判所の「検認手続き」が不要になる
- 紛失や改ざんのリスクを防げる
- 登録された人しか閲覧できない(プライバシー性も◎)
※事前予約と本人の出頭が必要です。
自筆証書遺言を作るときのチェックリスト
✅ 日付は明確に書いたか?
✅ 氏名・押印は自筆で行ったか?
✅ 財産の内容と受取人は具体的に書いたか?
✅ 書いたことを誰かに伝えてあるか?
✅ 保管場所は明確か?もしくは法務局へ提出したか?
まとめ:簡単に見えて奥が深い。それが自筆証書遺言です。
自筆証書遺言は、気軽に作れる一方で、形式ミスや内容の不備があると無効になってしまうこともあります。
「せっかく遺言を残したのに、かえって家族に迷惑がかかった…」
そんなことにならないよう、作成前には司法書士など専門家に一度チェックを依頼するのが安心です。
遺言書の作成・チェックは司法書士法人ホワイトリーガルにおまかせください
当事務所では、自筆証書遺言の作成サポートや、法務局保管制度の申請支援も行っています。
「まずは話だけ聞いてみたい」という方も、ぜひお気軽にご相談ください。
ここまでで、今回のブログ「自筆証書遺言を作成する上で気を付けるポイントを司法書士が解説!」のテーマの解説は以上になります。
当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、遺言書作成についての無料相談だけでなく、相続放棄や家族信託など相続に関連するお悩みについても無料でご相談することができます。
ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用していただきたいと思います。
 カワウソ竹千代
カワウソ竹千代遺言書作成でのお悩みについては、お気軽に当事務所までご相談をしてくださいね。



それでは、司法書士の久我山左近でした。