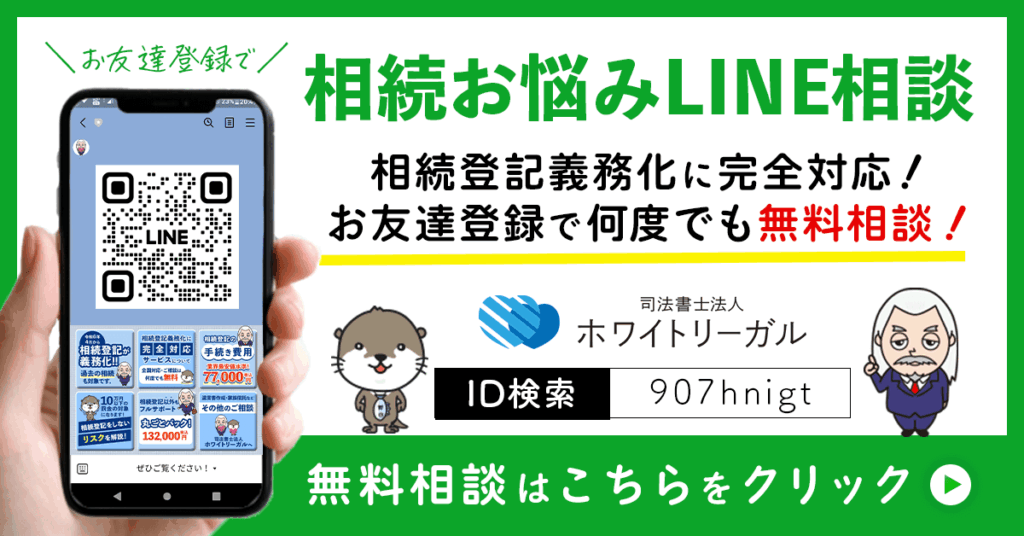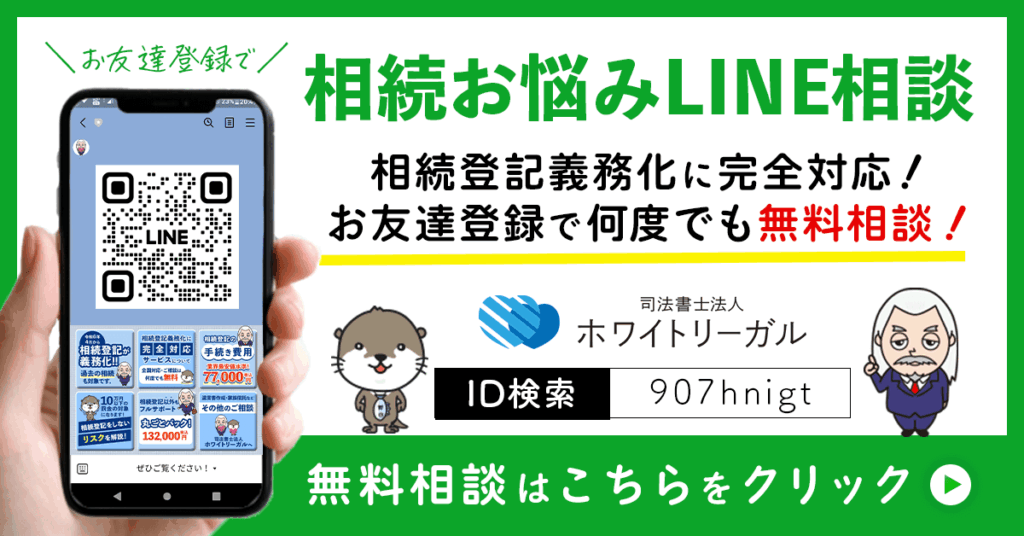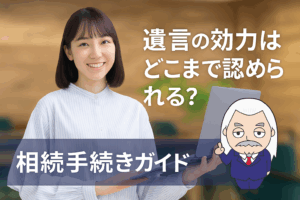こんにちは、「相続手続きガイド」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
相続の場面で「寄与分」という言葉を耳にすることがあります。
初めて聞く方には少し分かりにくいかもしれませんが、実際の相続手続きで重要な役割を持つ制度です。
寄与分とは、相続人の中で被相続人の財産形成や維持に特別に貢献した場合、その分を相続分に上乗せして考慮できる制度です。
この制度を理解しておくと、相続人間の公平を保ち、トラブルを避けることができます。
この記事では、司法書士の久我山左近が専門家の視点から、相続の場面で重要になる「寄与分」について、基本的な意味から実際にどのような場合に適用されるのか、さらに計算方法や具体的な算定例、請求する際の注意点まで丁寧に解説します。
専門用語はできるだけ噛み砕き、実際の数字や日常のケースを交えているため、初めて相続を経験する方でも理解しやすくなっています。
今まさに相続手続きを進める方」はもちろん、「将来のために知識を整理しておきたい方」にも役立つ内容です。
お友達登録するだけで相続のお悩みが解決できる!相続お悩みLINE相談!
相続人の貢献を公平に評価する「寄与分」の基礎知識と計算方法を解説!
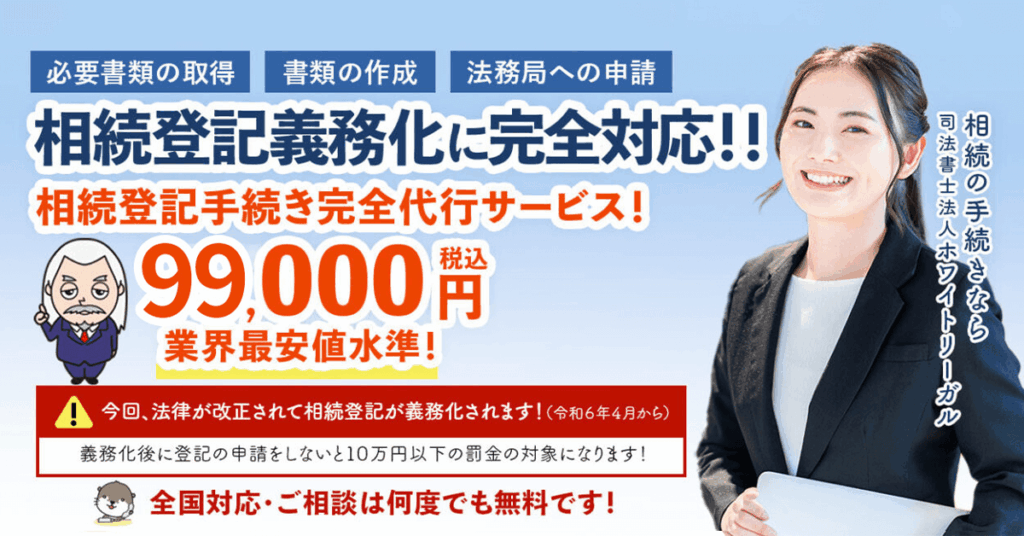
「相続無料相談のページを少し見てみる!」

「相続無料相談のページを少し見てみる!」
寄与分とは?
寄与分とは、相続人の中で被相続人の財産を増やす、または維持するために特別な貢献をした人が受け取れる相続分の加算分です。
例えば、同居して介護をしていたり、事業の手伝いで財産の増加に貢献した場合などが該当します。
寄与分が認められる具体例
- 介護・看護
- 高齢の親の介護を行い、施設費用を節約した場合
- 事業への貢献
- 家族経営の会社で働き、売上や資産増加に貢献した場合
- 財産管理や投資の補助
- 不動産の管理や運用で資産を増やした場合
※日常的な家事や生活費の負担は基本的に寄与分には含まれません。
寄与分の計算方法
寄与分の金額は、相続財産にどれだけ貢献したかを金額で評価して決まります。
計算式は以下の通りです。
寄与分 = 寄与による財産増加額 × 被相続人全体の相続財産に占める割合
計算例
- 相続財産:2,000万円
- 介護による節約分:300万円
寄与分として、相続財産2,000万円の中から300万円を加算して相続分を調整します。
これにより、寄与分を受けた相続人の公平性が保たれます。
寄与分を請求する際の注意点
- 遺産分割協議で全員の合意が必要
- 具体的な貢献内容や金額の証明が必要
- 揉めやすい場合は専門家に相談
寄与分は法律で認められていますが、適用される範囲や金額の算定には専門的な判断が必要です。
まとめ
寄与分は、相続人の特別な貢献を評価し、公平な相続を実現するための制度です。
- 介護や事業への貢献など、具体的なケースで考慮される
- 計算は貢献度に応じて相続財産から加算される
- 複雑なケースでは専門家の助言が安心
相続手続きをスムーズに進めたい方は、ぜひ本記事を保存して参考にしてください。
相続のご相談は司法書士法人ホワイトリーガルへ
相続手続きや寄与分、特別受益など、複雑な相続の問題は一人で抱え込まず、まずは専門家にご相談ください。
司法書士法人ホワイトリーガルでは、初回相談から丁寧に対応し、手続きのスムーズな進行や相続人間のトラブル回避をサポートいたします。
ここまでで、今回のブログ「寄与分とは?相続における意味と計算方法を司法書士が詳しく解説!」のテーマの解説は以上になります。
当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、相続手続きについての無料相談だけでなく、相続放棄や家族信託など相続に関連するお悩みについても無料でご相談することができます。
 カワウソ竹千代
カワウソ竹千代相続の手続きでのお悩みについては、お気軽に当事務所までご相談をしてくださいね。



それでは、司法書士の久我山左近でした。