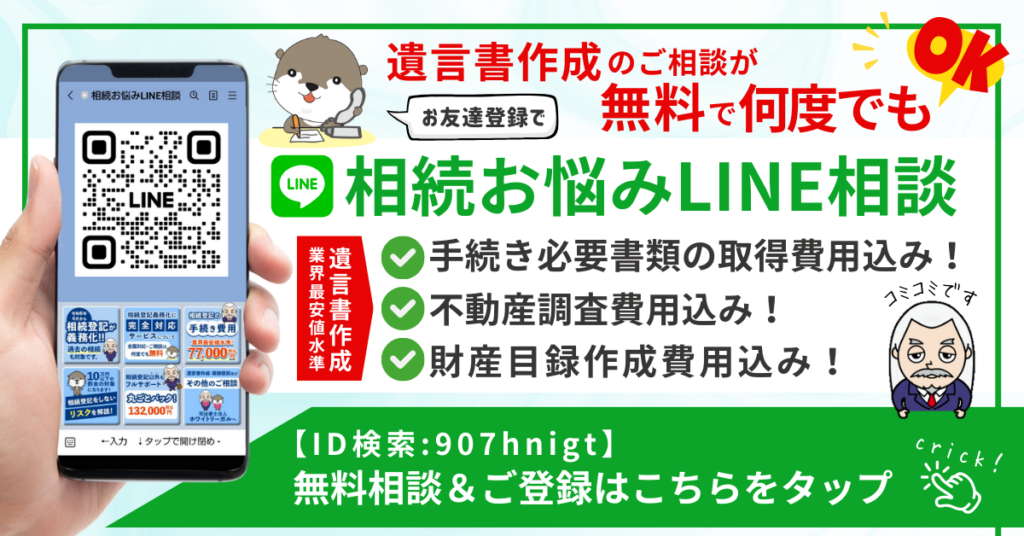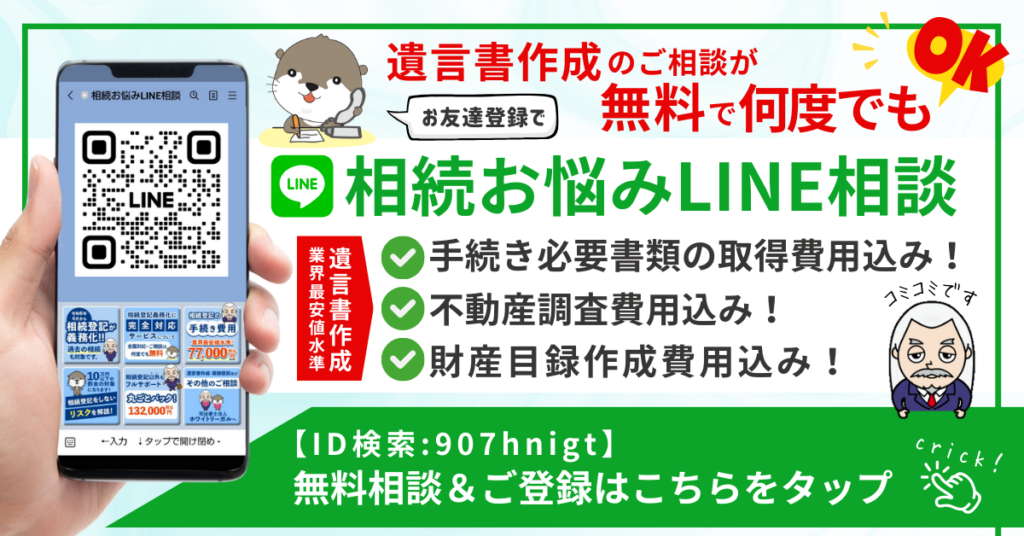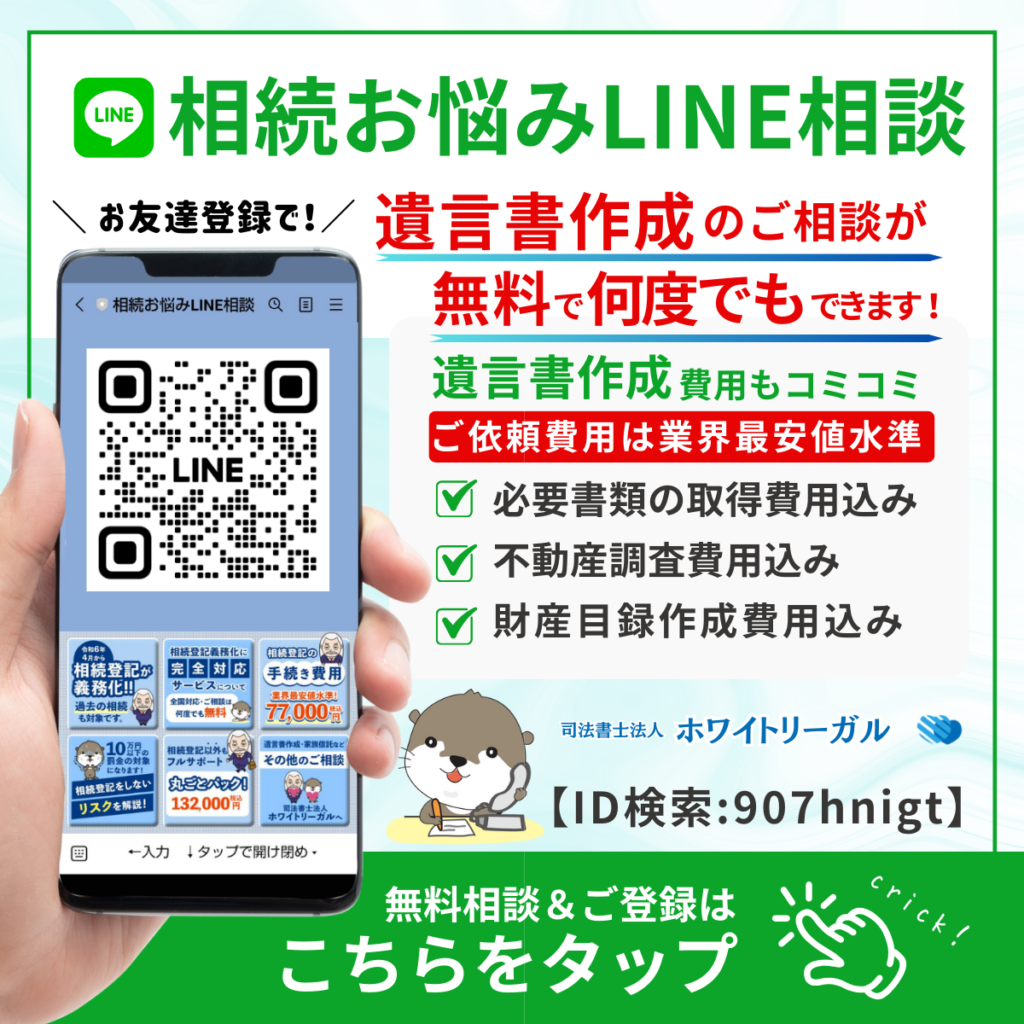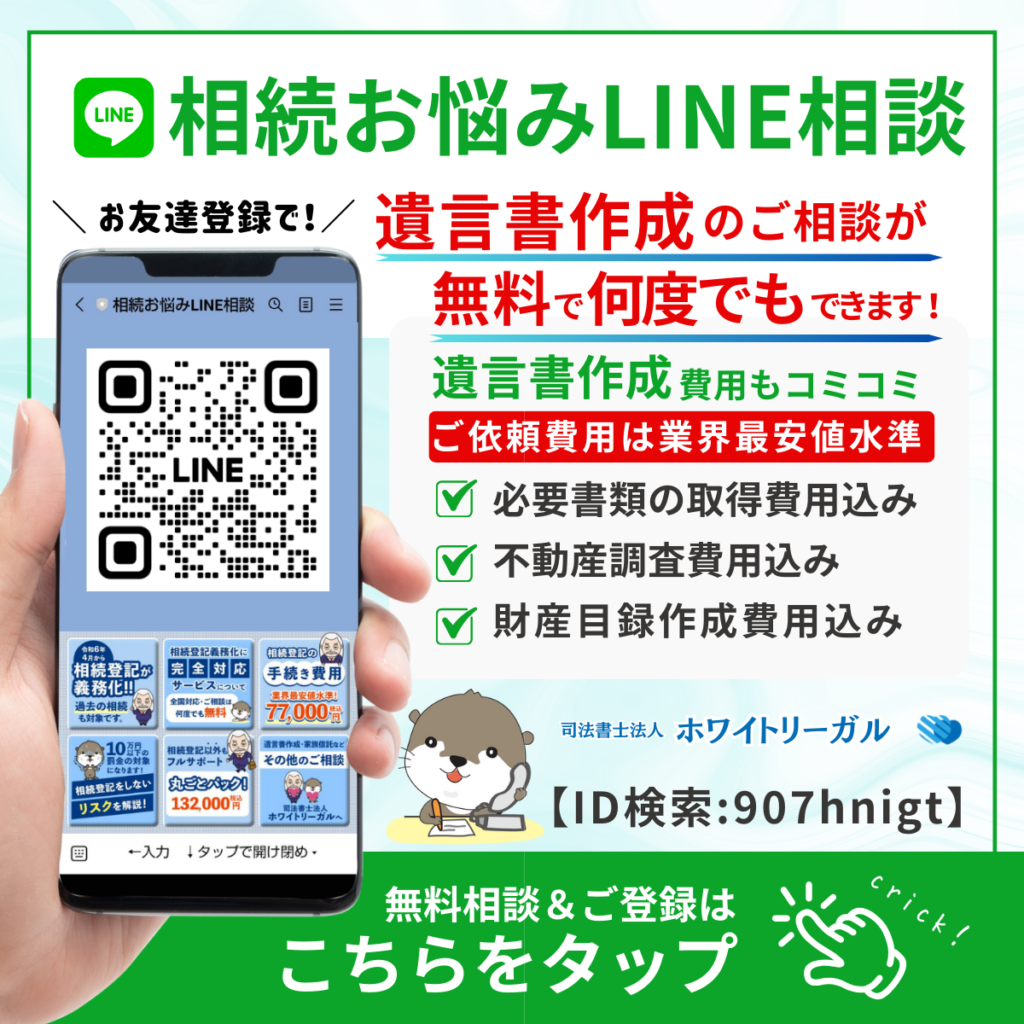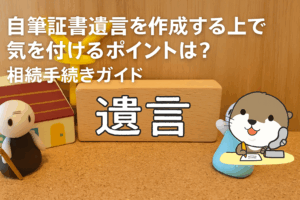こんにちは、「相続手続きガイド」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
遺言書を書いた後に、「財産の内容が変わった」「家族との関係が変わった」「書いた内容に不安が出てきた」
ということは、誰にでもあり得ます。
そんなときに気になるのが「遺言書って、あとから書き直せるの?」という疑問。
結論から言えば、遺言書はいつでも何度でも書き直すことが可能です。
ただし、正しい方法で変更しなければ、思わぬトラブルにつながることもあります。
この記事では、「遺言書を書き直したい」「内容を一部だけ変更したい」と思ったときに、どんな方法や手続きが必要なのか、また注意すべき点は何かを具体例を交えて司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
あとから慌てないためにも、知っておきたい実務的なポイントをまとめました。
お友達登録するだけで遺言書作成のお悩みが解決できる!相続お悩みLINE相談!
遺言をあとから直したいときに知っておくべき基本を解説します!
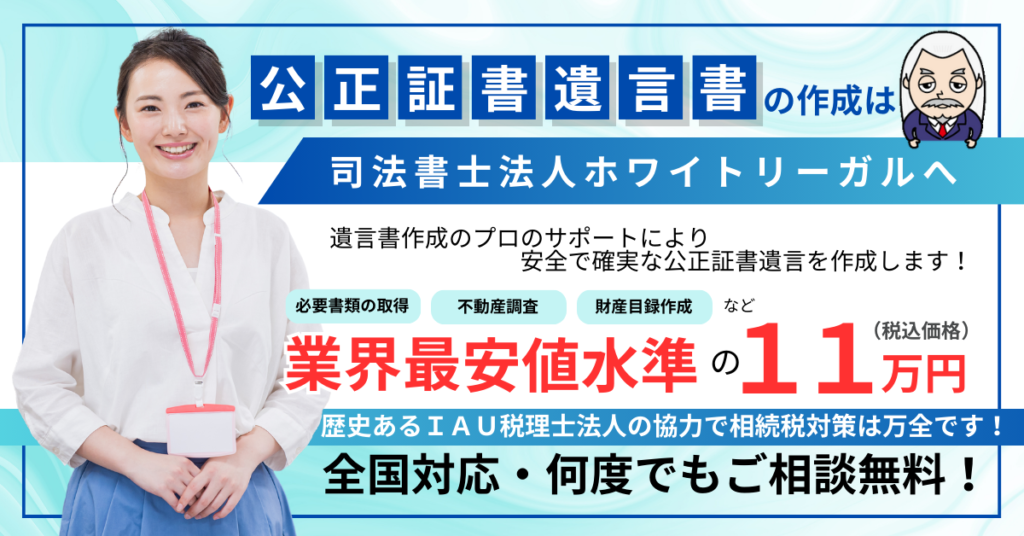
「遺言書作成ご相談のページを少し見てみる!」
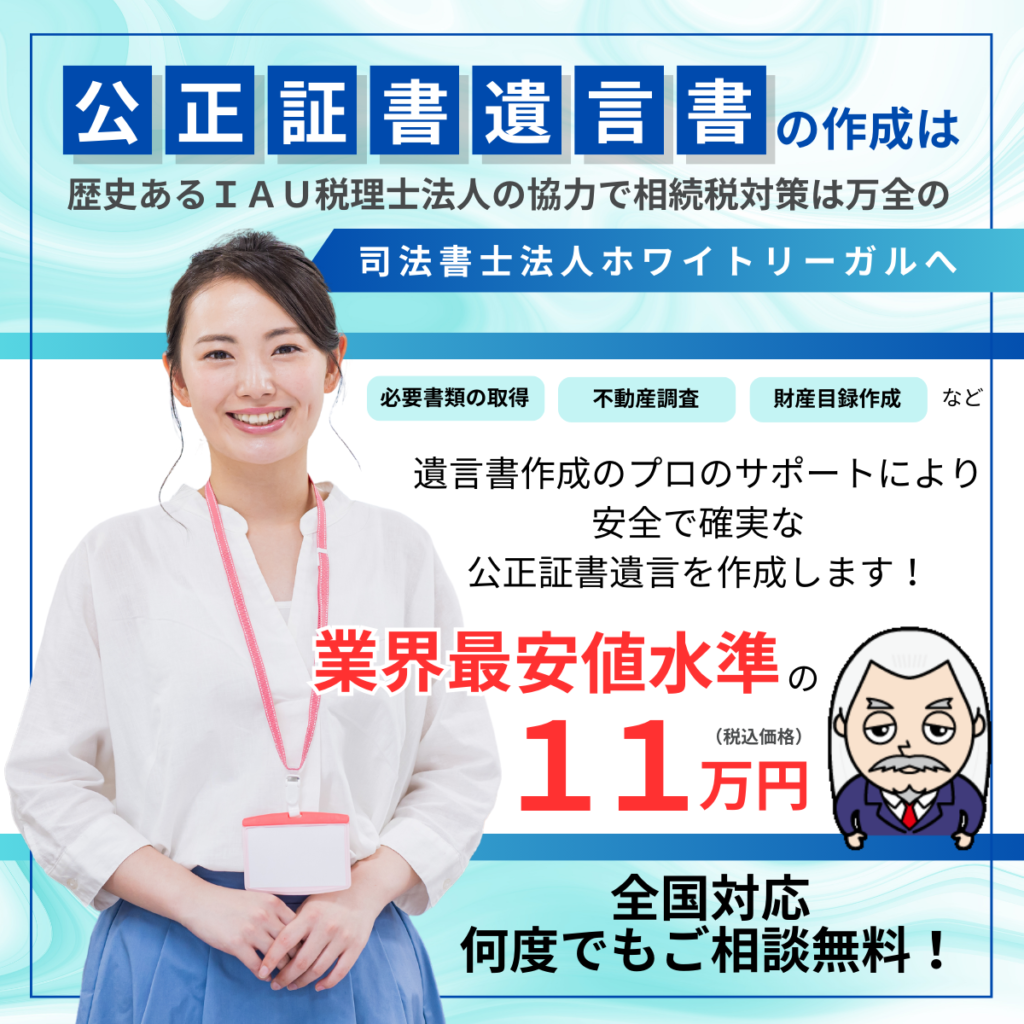
「遺言書作成ご相談のページを少し見てみる!」
遺言書は「自由に変更・撤回できる」
民法では、遺言書について以下のように定められています。
遺言者は、いつでも、何度でも、内容を撤回または変更することが可能です(民法1022条)。
つまり、いったん作った遺言書に縛られる必要はありません。
その後の状況や気持ちの変化に応じて、書き直しや追加ができる柔軟な仕組みになっているのです。
【1】書き直す場合:新しい遺言が古いものに優先
遺言書を丸ごと新しく書き直す場合は、新しい日付の遺言書が優先されます。
このとき、古い遺言を明示的に「撤回する」と書かなくても問題ありません。
ただし、内容が一部しか違わない場合は、どの部分が有効か争いになることも。
不安な場合は、「○年○月○日付の遺言はこれを撤回する」などの文言を入れておくと安心です。
【2】一部だけ変更する場合:遺言書の「付言」や「訂正」も可能
全文を新しく書き直すのではなく、「特定の財産の相続人だけを変えたい」「一部の表現を修正したい」
というケースもあるでしょう。
この場合、2つの方法があります:
- 訂正方法(※自筆証書遺言の場合) → ルールに沿って、訂正印と署名が必要。少し手間がかかります。
- 変更を加えた「新たな遺言書」を作成 → 一部の修正でも、新しい遺言として作成すれば間違いがありません。
【3】口頭やメモでは撤回にならないので注意!
よくある誤解ですが、「家族に口頭で“前の遺言は無効にしたい”と伝えた」「日記やメモに“あの遺言はやめたい”と書いた」というような行為は、法的に撤回や変更とみなされません。
遺言書の変更・撤回には、正式な書式と手続きが必要です。
気持ちが変わったときは、できるだけ早めに新しい遺言を作り直しましょう。
【4】公正証書遺言も変更・撤回できる
「公正証書遺言は、あとで変えられないのでは?」と心配される方もいますが、こちらも問題なく変更・撤回ができます。ただし、再度公証役場での手続きが必要となるため、費用や時間はかかります。
まとめ:遺言は「更新できる」からこそ、今すぐ準備して大丈夫
遺言書は、人生の変化に合わせて柔軟に内容を見直すことができる仕組みです。
そのため、「まだ完璧じゃないから書かない」のではなく、
まずは書いてみることが大切です。
そして、環境や家族との関係が変わったら、無理なく何度でも「更新」すればよいのです。
遺言書を変更・撤回したいと感じたら、司法書士法人ホワイトリーガルへ
- 古い遺言と新しい遺言が矛盾しないよう注意
- 法的に有効な形式を守ること
- 不安な場合は司法書士や弁護士などの専門家に相談すること
遺言書は「遺すこと」がゴールではなく、
遺された人にきちんと「届くこと」が本当の意味での完成です。
司法書士法人ホワイトリーガルでは、遺言書の作成や変更・撤回に関するご相談も承っております。
「以前書いた遺言を変更したいけど、どうすればいいの?」「新しく書き直したら、古い遺言はどうなるの?」といった疑問やお悩みがある方も、どうぞ当事務所までお気軽にご相談ください。
ここまでで、今回のブログ「遺言書はあとから書き直せる?遺言書の撤回や変更の方法を解説します」の解説は以上となります。
当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、遺言書の作成・見直しはもちろん、相続放棄や家族信託など、幅広い相続に関するお悩みについても、無料相談を実施しています。
「もしものときに備えて、今のうちに準備しておきたい」そんな方は、ぜひお気軽に当サイトの無料相談をご利用ください。
 カワウソ竹千代
カワウソ竹千代相続手続きでのお悩みについては、お気軽に当事務所までご相談をしてくださいね。



それでは、司法書士の久我山左近でした。