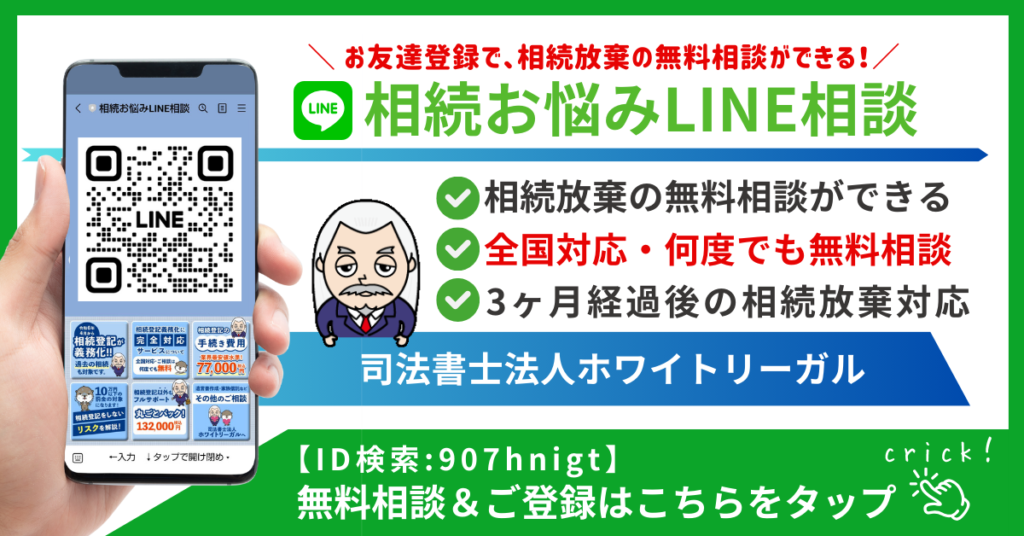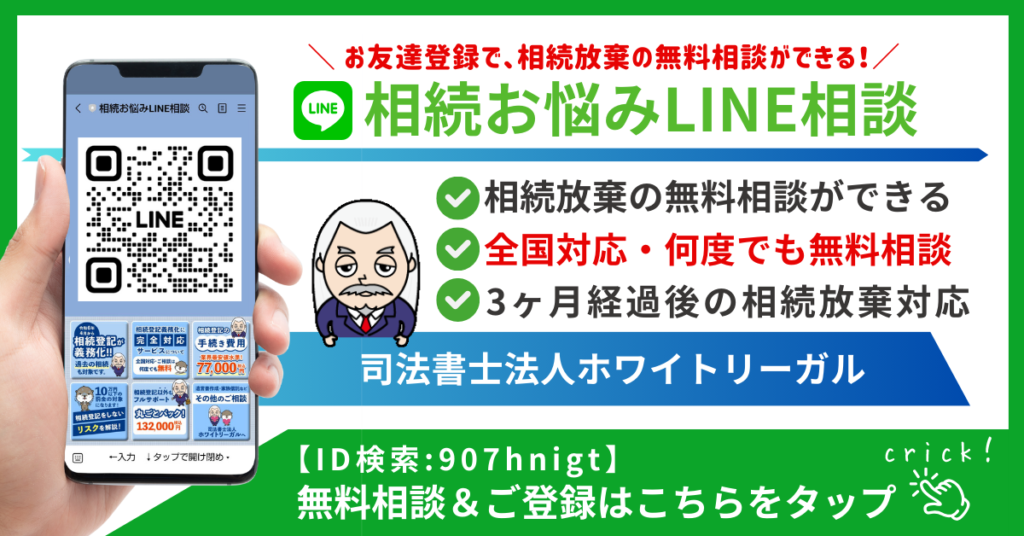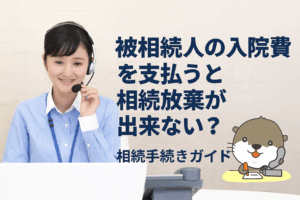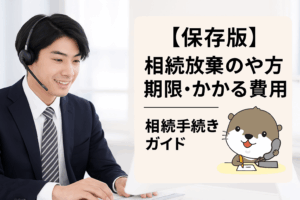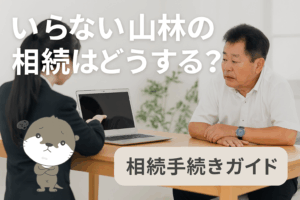こんにちは、「相続手続きガイド」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
「親の借金は相続したくない」「遺産はいらないから関わりたくない」──そう思ったときに検討するのが“相続放棄”です。
しかし、相続放棄の手続きは期限がある上に、必要な書類も多岐にわたります。
書類の不備や提出の遅れは、放棄が認められない原因にもなりかねません。
この記事では、相続放棄に必要な書類の一覧と取得方法を、司法書士の久我山左近がわかりやすく解説します。
初めての方でもスムーズに準備できるよう、実務に即したポイントを整理していますので、ぜひ参考にしてください。
お友達登録するだけで相続放棄のお悩みが解決できる!相続お悩みLINE相談!
相続放棄の手続きで必要な書類一覧と取得方法をわかりやすく解説!
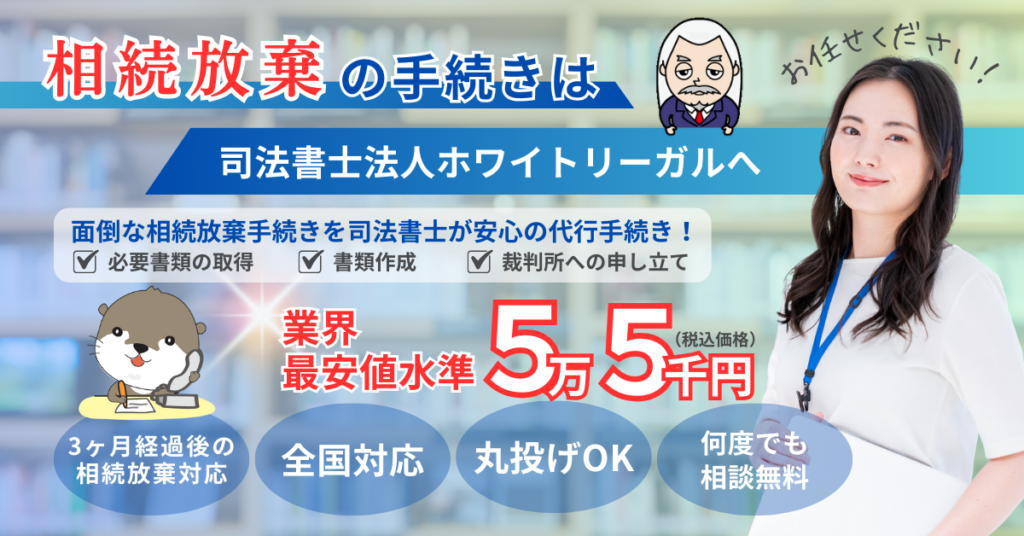

1. 相続放棄とは?手続きの概要を簡単に解説
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産や借金など、一切の相続を受け継がないことを家庭裁判所に申述して認めてもらう手続きです。
放棄が認められると、初めから相続人ではなかったものとみなされ、借金の請求を受けることもなくなります。
ただし、相続の開始(被相続人の死亡)を知ってから3か月以内に申立てを行う必要があります。この期限を過ぎると、相続を承認したと見なされる可能性があるため、早めの対応が重要になります。
2. 相続放棄に必要な書類一覧【最新版】
家庭裁判所に提出するために、主に以下の書類が必要です。
▼申述人(相続放棄をする人)が用意するもの
- 相続放棄申述書(所定の様式あり)
- 申述人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 被相続人の戸籍(出生から死亡まで)
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
▼場合により必要なもの
- 他の相続人が放棄済みであることを証明する戸籍
- 遺産分割協議書(誤って手を付けていないことの証明)など
※相続人が未成年の場合や複数の相続人が関係する場合、追加書類が必要になることもあります。
3. 各書類の取得方法と注意点
●戸籍謄本(被相続人・申述人)
本籍地のある市区町村役場で取得します。
被相続人については「出生から死亡までの連続した戸籍」が必要なので、複数の戸籍が存在するケースもあります。
●住民票除票・戸籍附票
被相続人の死亡時の住所地の市区町村役場で取得します。住民票除票は死亡後5年で消除されるため、取得はお早めに。
●相続放棄申述書
家庭裁判所の窓口またはホームページからダウンロードできます。
書き方に不安がある方は、専門家に確認してもらうことをおすすめします。
4. 相続放棄の手続きの流れと提出先
手続きの基本的な流れは以下のとおりです。
- 必要書類の収集
- 相続放棄申述書の作成
- 管轄の家庭裁判所へ提出(被相続人の最後の住所地)
- 裁判所からの照会書への回答
- 相続放棄受理通知書の受領
手続きの期限は3か月以内です。書類の不備があると差し戻され、間に合わない可能性もあるため、余裕を持って準備しましょう。
5. よくある質問Q&A【相続放棄と書類編】
Q. 書類のコピーではだめですか?
A. 原則として、戸籍などは「原本」が必要です。コピーは認められません。
Q. 書類に不備があった場合、やり直せますか?
A. 軽微な不備であれば修正の指示がありますが、期限を過ぎると放棄が無効になる場合もあります。
Q. 他の相続人が放棄しているか確認したい場合は?
A. 裁判所に確認をとるか、戸籍で相続関係をたどる必要があります。
6. 書類準備が不安な方へ|司法書士に相談するメリット
相続放棄は、一見シンプルな手続きに見えて、戸籍の収集や書類の整合性など意外と手間がかかる作業です。
特に、「戸籍がつながらない」「期限が迫っている」などの場合は、専門家に依頼することでスムーズに解決できます。
司法書士に依頼すれば、書類の収集から申述書の作成、家庭裁判所への提出サポートまでワンストップで対応可能です。不安やトラブルを未然に防ぐためにも、ぜひ専門家への相談をご検討ください。
どうでしょうか、今回のブログ「【保存版】相続放棄に必要な書類とは?手続き前に必ず確認しよう!」のテーマの解説は以上になります。
当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、相続放棄のお悩みに関する無料相談だけでなく、相続の手続き全般に関して無料相談を受け付けています。
ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用して相続のお悩みを解決していただきたいと思います。
 カワウソ竹千代
カワウソ竹千代相続放棄に関する何か疑問点やご質問などがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください!



それでは、司法書士の久我山左近でした!